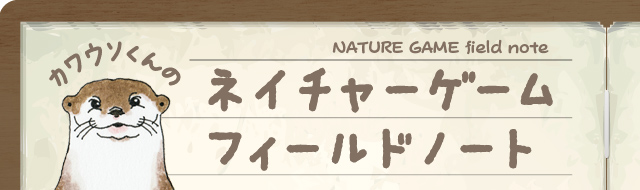-
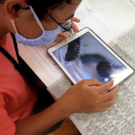
STEAM教育とは、科学・技術・工学・芸術・数学などの手法を駆使して、
子どもたちが、今そこにある〝課題〟を発見し、解決する力を育む考え方のこと。
どのように実践でいかしていけばよいのでしょうか?
-
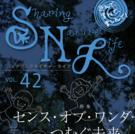
「センス・オブ・ワンダー」 この言葉を知っている人は、多いのではないでしょうか。
これは、「神秘さや不思議さに目を見はる感性」(『センス・オブ・ワンダー』p23)を意味し、アメリカの作家で『沈黙の春』を著して環境保護運動のきっかけを作ったレイチェル・カーソンの代表作として広く知られています。
彼女の著作を翻訳し、その思想や自然への愛情を多くの人に伝え続けてきたのが上遠恵子さん。
94年目の春を迎えた上遠さんの目に今映るものや〝自然〟と〝子ども〟に向き合う大人たちに伝えたいことを伺いました。 -
花を楽しむネイチャーゲームライフスタイル

(2024.07.23記事作成)
花は好きですか?どんな風に楽しんでいますか?今回ご紹介するのは、更にもう一歩深く踏み込んで花を楽しむ方法。ネイチャーゲームで五感を使って、余すことなく花の魅力を知りましょう!
-

(2024.07.10記事作成)
フレーム片手に風景を〝切り取る〟〈森の美術館〉。フレームのサイズは大小さまざま、形もさまざま。ちょっとした時間に楽しめる新しい「カタチ」も登場。もちろん手作りしても楽しい。保育園の送りや、お迎えなど、毎日の「歩く」を、自然を楽しむ時間に!
-
自然にふれて生産性を上げるリラックス方法3選ライフスタイル

(2024.07.09記事作成)
ネイチャーゲーム〈雲見〉などを始めたとした 日々の生活に簡単に取り入れられるリラックス法ををご紹介します。
-
幼児としぜん保育・幼児教育

「ネイチャーゲーム認定園」とは、シェアリングネイチャーの考え方を取り入れた自然遊びを体験できる保育園・保育所・幼稚園・こども園・森のようちえんです。
「自然体験が子どもにどう影響するの?」「ネイチャーゲーム認定園に子どもが通うメリットとは?」そんな保護者の疑問に専門家がお答えします! -
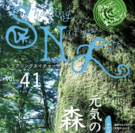
森林セルフケアコーディネーターとして 活動している、 みかぽんこと 赤居実花さん 。 人と自然、心と体の 繋 がりを学び続け、 さまざまな手法で 心と体を 元気にする サポートをしています。 自ら を 〝 元気のソムリエ 〟 と 称する 赤居さん。 森林セルフケアって? 元気のソムリエってどういうこと? 一緒に 森を歩 きながら 、 教えてもらいました。 -

自然とふれあう中で生まれる〝問い〟。
この〝問い〟が、私たちを取り巻く課題を解決する「糸口」になる !?
ちょっとだけ視点を変えて、ネイチャーゲームを捉え直す新連載スタートです!
-
特集:ドングリの思うツボ(SNL 40号/2023年10月号)ライフスタイル

見つけて、拾って、集めて...それだけでも楽しい、ドングリ。
さらにもっとおもしろくする秘訣は「ドングリメガネ」
心に好奇心のメガネをかけて、一つひとつの違いに気づき、そのすべてを楽しむ〝見方〟のこと。
そんな「ドングリメガネ」をおすすめするゲッチョ先生こと盛口満さん。
とことんドングリを探究する先生からドングリの魅力をお聞きしました。 -

(2023.12.25記事作成)
自分が森や自然の一部だと感じるための第一歩〈森林浴のエクササイズ〉についてご紹介します。
-
学童指導員向け「安全つくり研修」小中学生の自然体験

(2023.11.07記事作成)
「学童の隣に林があって、そこでの自然遊びをしたいけど、遊び方を知らない」
だけど「自然には危険もあるから、なかなか外に出かける難しさもある」
そんな「安全」と「自然あそび」の両立についての悩みに、ネイチャーゲームと、KYT(危険予知トレーニング)を組み合わせた研修でお答えしてきました。
学童指導員向け「安全つくり研修」の様子をお伝えします。
-

(2023.10.12記事作成)
「ポタポタ」「カサカサ」「サラサラ」などリズムよく重ねた擬態語・擬音語を使って、自然の様子を表現して楽しむ...表現することのおもしろさや、自然のさまざまな表情、感性の違いに気づけるネイチャーゲーム。
-
自然の中から同じ自然物探しに挑戦!〈同じものを見つけよう〉小中学生の自然体験

(2023.10.12記事作成)
リーダーが見せる自然物を覚えて、同じものを探す活動。同じものといっても実は、〝同じ〟じゃない。よく観察して見比べて違いに気づく、そのきっかけにもなるネイチャーゲームです。
-

(2023.9.23記事作成)
自然を楽しみ、自然と遊び、自然から学ぶ・・・自然と暮らすアイディア集
-
特集:クマとうんちに誘われて(SNL 39号/2023年7月号)ライフスタイル

自分と同じくらいか自分よりも大きなクマが森の中で何を食べ、どう生きているのか。自分は同じように森で暮らせるだろうか?
──そんな疑問からクマ研究の道へと進んだ後藤優介さん。野生のクマを追い、うんちをはじめ、あらゆる痕跡からその姿をひも解いてきました。
多くの発見がなされた一方で、いまだ謎がある奥深い相手。
「わからない」ことのおもしろさを自らの体・感覚を使って「わかった!」ときの感激。
後藤さんが語るクマへの情熱から、〝自分だけの好き〟を追求する楽しさが見えてきます。
-
耳を澄ます...それだけで、世界を変える〈音いくつ〉ライフスタイル

(2023.07.11記事作成)
閉じることのできない感覚、「聴覚」。にも関わらず意識を向けているかどうかで、聞こえ方がまったく変わる不思議な感覚。そして聞こうとするとき、人は静かになる。「自然の音に耳を澄ませてみよう」、それだけであなたも、そしてもちろん子どもたちも、心穏やかな瞬間に出会えます。
-

(2023.7.5記事作成)
自然を楽しみ、自然と遊び、自然から学ぶ・・・自然と暮らすアイディア集
-
私は誰...?〈私は誰でしょう〉で楽しく学ぶ「動物の生態」小中学生の自然体験

(2023.7.5記事作成)
教育の現場において「体験したことあるよね?の前提」が崩れて(?)久しい今日この頃。幼少期の外遊びをはじめ、暮らしの中にある自然との関わりからの「体験」の多様性が下がってきています。そんなときだからこそ、〈私は誰でしょう〉を紹介します!
-
「自然がいいね」と思える。親子キャンプでネイチャーゲーム小中学生の自然体験

(2023.4.27記事作成)思春期真っ只中の息子と2人でキャンプへ。あいにくの雨天や、夜も、「いいね」と感じさせてくれるネイチャーゲームの魅力を紹介します。
-
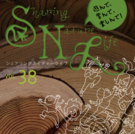
「木こり」と聞いて、どんな仕事をイメージしますか?
〝木こりのタジー〟として、森林の手入れ、薪の生産はもちろん小・中学生の森林体験や環境教育、市場で売れない木材の活用事業などを展開し、ネイチャーゲームリーダーとしても活動している田實健一さん。
日々、新たな林業の確立に奮闘している田實さんにとって木こりとは?理想の森とは?どんな姿なのか伺いました。